法人について
理事長挨拶

「炎症性腸疾患(Inflammatory bowel disease : IBD)」と聞いて、皆さんはどのような印象を持たれるでしょうか?慢性的な腹痛や下痢、食事制限、入退院の繰り返し…。そんなイメージを抱く方も多いかもしれません。実際、IBDと診断された患者さんやそのご家族の多くが、将来への不安や孤独感に直面します。1972年に難治性疾患の一つとして潰瘍性大腸炎が指定され、翌年研究会議(班会議)が組織され、その翌年にはクローン病もスタートしました。この二つの疾患を合わせて「炎症性腸疾患」と総称されます。
以前は治療法も少なく難病と考えられました。しかし、医療の進歩とともに、IBDを抱えながらも自分らしい生活を送ることは、今や十分に可能な時代となりました。原因不明で根本治療はまだ開発されていませんが、今や炎症を抑え(寛解導入)て、炎症のない状態を持続させる(寛解維持)治療法が進歩して、殆どの患者さんが、症状のない状態で生活ができるようになってきました。しかし、再燃するではないかとか、トイレが近くにないと不安とか、軽い症状だけども日常生活に支障をきたすなど、人には言えない不安が続いている方も多くいます。不安なく学校に通い、仕事をし、趣味を楽しみ、家族と笑い合う。そんな「当たり前の日常」を、IBD患者さんが取り戻し、彩っていけるように――その想いから「IBD患者さんの日常を彩る会」は生まれました。実際診療に携わる医師・看護師・栄養士・薬剤師など医療従事者と治療法を提供してくれる製薬会社の専門家が相談し、自分たちが気づいていない患者さんの日常の悩みを解決すべく、一堂に会するものとして、「IBD患者さんの日常を彩る会」の活動を図っていきたいと考えています。
私たちの会では、患者さん同士の交流や情報共有、医療者との対話の場を設けることで、病気と向き合う力を育み、前向きな一歩を後押ししています。また、IBDに対する社会の理解を深めるための啓発活動にも力を入れており、患者さんが安心して暮らせる環境づくりを目指しています。会の具体的な行動として以下を考えています。
- 患者さんの会との密接な連携により患者さんが専門医に聞きたいことの専門医からの発信
- 各製薬会社が持つ患者さんへのHPの紹介とリンクによる広い情報提供
- 本会からの公平で偏らない、IBDの最新情報の発信
- 患者さんが困っている社会環境や公共施設の改善
- 全国の専門施設の紹介や取次
IBD患者さんの数はまだまだ増加しており、もしかすると、あなたのすぐそばにもIBDと共に生きる方がいるかもしれません。だからこそ、正しい知識と温かな理解が、今、社会に求められています。
今後も皆様のご意見や質問をいただき、本会を患者さんの日常生活に役立つものとして確立していきたいと思っています。「病気があっても、人生は彩れる」――この言葉を胸に、私たちはこれからも、IBD患者さん一人ひとりの「日常」を支え、共に歩んでいきます。
一般社団法人
IBD患者さんの日常生活を彩る会
理事長 日比 紀文
名称
一般社団法人 IBD患者さんの日常生活を彩る会
目的
当法人は、潰瘍性大腸炎及びクローン病などの炎症性腸疾患に関する社会啓発・支援活動を通して、炎症性腸疾患患者及びその家族のクオリティ・オブ・ライフの向上ならびにノーマライゼーションの実現に寄与することを目的とする。
理事

久松 理一
杏林大学医学部 消化器内科学 教授

中村 志郎
互恵会 大阪回生病院 消化器内科 IBDセンター長
中村 志郎からのメッセージ
IBD患者さんの生活を彩る会に理事として参加させて頂いております中村志郎でございます。私が富山医科薬科大学(現 富山大学)を卒業し、医師となったのは1986年でありました。大阪出身ということで、大阪市立大学(現 大阪公立大学) 第三内科に入局させて頂き、研修医時代のオーベン(指導医)が、大腸グループ所属していたことから、炎症性腸疾患(IBD)の患者さんを担当させて頂く機会が多くあり、診療経験を重ねる中で、自然とこの疾患領域に進み、気がつくとはや40年という月日がたっていたというのが正直な実感です。 私が新米医師だった1980年代から2000年頃までのIBDの内科治療は、潰瘍性大腸炎(UC)はサラゾピリンとステロイド(CS)、クローン病(CD)は栄養療法がほとんど全ての様な状況で、出来ることが限られていたため難治性UCの患者さんは、CS依存から中心性肥満や骨粗鬆症などの合併症を併発する場合があり、CD患者さんも栄養障害から痩せている方や頻回に入退院や手術を繰り返す方が多い傾向にありました。2000年以降、特にこの10数年の間、多くの生物学的製剤(注射剤)や新しい低分子薬(経口剤)が登場によってIBDの内科治療は急速に進歩し、内科治療の成績も非常に改善されてきています。実際に、近年では世界的にIBD患者さんの手術率や入院率が低下してきていることが報告されていますし、自分の日々の診療を振り返っても2000年以前に比べると治療経過の安定した患者さんが増えてきていることを実感しています。しかし、依然IBD患者さんは年々増加の一途をたどっており、やはり治療に難渋する場合も多く、診療を通しIBDという疾患が患者さんの人生や、社会に与える影響は、まだまだ大きいものがあると実感しております。特にIBD患者さんは、進学・就職・結婚・子育てなど人生でも重要で負荷の高い出来事が重なるAYA世代に罹患する場合が多いため、社会的な影響は甚大であり、患者さんを取り巻く社会的状況は、2000年以前の頃と実はあまり変わっておらず、IBDという疾患の社会的な理解や、患者さん自身が日常生活の中で経験する不自由など諸問題の具体的な改善も非常に重要であると思っております。今回、日比先生の患者さん中心の強い思いに賛同し、この「IBD患者さんの生活を彩る会」に参加させて頂き、日比理事長をはじめ、理事の皆様、会員の皆様と伴に、IBD患者さんの社会的な環境改善、ならびに本法人発展の一助になれればと願っております。どうかよろしく御願い申し上げます。
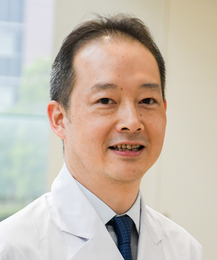
土屋 輝一郎
筑波大学消化器内科 IBDセンター部長
土屋 輝一郎からのメッセージ
みなさん、こんにちは。私は1995年に山梨医科大学を卒業して、研修医1年目から東京医科歯科大学医学部附属病院(現 東京科学大学病院)にて内科や消化器内科の診療を行なってきました。大学院を卒業してからは主に基礎研究に多くの時間を費やしてきました。何故かというと、現在の医療よりもさらに先の医療のために、いま解決できていないことをテーマとして取り組みたいと考えたからです。炎症性腸疾患はその名前の通り、腸に炎症が起こる病気です。そのため、炎症が起こる仕組みや炎症を抑える治療薬に関する研究が多く行われ、現在では多くの治療薬が使えるようになっています。一方で、炎症を抑えるという同じ種類の治療薬であり、治療薬が増えても未だに良くならない患者さんが多いことも事実です。私は以前から腸の粘膜上皮に注目してきました。腸粘膜は腸内と体内を区切るいわばお城の壁のような役割をしています。お城の壁が崩れることは粘膜がないことを意味しており、潰瘍になってしまいます。お城の壁が無くなって潰瘍になると、雑菌など様々な物が体内に侵入してきて炎症のきっかけになってしまいます。そのため、現在の治療目標は炎症を抑えるだけでなく、潰瘍を治すことがゴールとなっていますが、潰瘍を直接治す効果がある治療薬はありません。そこで、なぜ城壁が崩れるのか?城壁を修復できる仕組みや治療薬があるか?をテーマとして取り組んでいます。将来的に今の治療で不足している部分を補えるように「更なる先」を目指しています。 話は変わりますが、2021年より筑波大学附属病院に異動し、これまでより多くのIBD患者さんを診療する機会が増えました。診察する際に、「お変わりありませんか?」と尋ねると、多くの患者さんは「変わりありません。」「大丈夫です。」と答えてくれます。その場では安心していましたが、先日、日比理事長から飛行機に搭乗する際のトイレ問題など様々な社会問題が解決されていないことを伺いました。つまり、病気としては「大丈夫」でも日常生活では「大丈夫ではない」ことに気付かされた次第です。基礎研究と社会問題はジャンルとしては全く異なる分野ですが、現在の医療では解決されていないことに対して取り組むという点では全く変わりがありません。医療の「更なる先」として、患者さんの日常生活をより豊かに彩るという本会の主旨に強く賛同し、参加させていただくことになりました。現在は、日本炎症性腸疾患学会のIBD専門医制度の発足に委員長として携わっており、日本全国のIBD診療施設の普及や専門医の育成に努めております。少しでも本会に貢献できるように活動していきますので今後ともよろしくお願いいたします。
平岡 佐規子
岡山大学病院 炎症性腸疾患センター センター長
平岡 佐規子からのメッセージ
炎症性腸疾患(IBD)の診療にしっかり携わり始めて約20年が経ちました。私の診療の目標は、IBD患者さんが同年代の人と同じように、さまざまなチャレンジができるように支えることです。もちろん病状が難しい方もおられ、理想論に聞こえるかもしれませんが、それでも私は常に目指しています。日々患者さんと向き合うなかで、その姿が私自身のモチベーションを高めてくれています。 仕事に関しても同じです。体調を第一に考えることは大前提ですが、「少し大変かもしれない」と思うくらいのチャレンジなら、応援したいと感じます。実際に、合併症があり病状も難しく、しかも過酷な職業に就いている患者さんがおられました。私は「辞めてしまうのでは」と思ったのですが、その方には全くその気がなく、むしろ仕事を続けたいという強い意志を持っていました。そこで私たち医療者も、それに応えたいと思い当時可能な治療を最大限に活用し、その方はなんとかその仕事を継続することができました。私は時に「もし病気がなければ、この方はもっと高いレベルで活躍できたのでは」と考えてしまうのですが、比較することに意味は無いと思いました。病状が安定していて長く続けられそうな仕事を選ぶことも立派なチャレンジですし、新しいことをやりたくなって転職するのもまたチャレンジです。自分に合った挑戦を見つけること、それに向かって動き出せること自体が大切だと思っています。 ただし、その挑戦を患者さんや医療者だけで支えるのには限界があります。社会の理解や仕組みが必要です。職場によって理解の度合いは異なります。とても理解ある上司や同僚がおられる環境もありますが、一方で、疾患特有の腹部症状や倦怠感のために「お腹が弱く、やる気がない人」と誤解されてしまうケースも少なくありません。こうした現実を変えていくため、私たちはIBD研究班や学会(JSIBD)で「IBD患者さんの就労支援」について議論を重ね、取り組みを進めています。そして、その実践の場として『彩る会』と連携しています。 私たちが目指しているのは、IBDだからといって特別に扱うことではありません。誰もが病気や体質にかかわらず、自分らしくチャレンジできる社会をつくることです。その第一歩として、身近なIBD患者さんの挑戦を支え、『彩る会』を通じて活動を広げていきたいと考えています。

長堀 正和
東京科学大学病院 ヘルスサイエンスR&Dセンター 准教授
長堀 正和からのメッセージ
所属名(「ヘルスサイエンスR&Dセンター」)を拝見いただくと、「何をしている人?」という印象を持たれると思いますが、わたくしは、1992年に東京医科歯科大学(現東京科学大学)を卒業し、初期研修を終えた後には、海外留学期間を含めて、一貫して、消化器内科及び炎症性腸疾患患者さんの診療と臨床研究に取り組んできました。 診療を通して思うことの1つに、検査や治療だけでなく、多くの患者さんやご家族にとって、日々の食事に関する疑問や不安がいかに大きいかという点があります。担当医や医師以外の医療職からの説明、患者家族向け講演会、書籍、SNSを含むネット情報やいわゆる口コミを含めて、食事に関する情報は入手しやすくなっているとは思いますが、それぞれの情報がどの程度の根拠があり正確なものかを判断することは決して容易ではないと思います。さらに、その内容を理解し、日々の食事において実践しようとする際に、場合によっては発信者の意図とは異なって理解、実践され、極端な食事制限により栄養障害は陥っている患者さんも経験します。また、患者さんの「食事療法」が、患者さんの「生活の質(クオリティーオブライフ)」に影響を与えるだけでなく、ご家庭の食卓に様々な影響、負担を与えていることも伺ってきました。 食事をめぐるこのような困難の原因の1つには、特定の食事、食物の有用性と安全性を検証するための臨床試験の実施が、薬などとは異なり極めて困難ということにあると考えています。詳細は割愛しますが、それでも、近年では、そのような臨床試験の研究結果も公表されていますので、この会においては、そのような情報も、分かりやすい解説を加えて提供していきたいと考えています。 食事に関して、現時点で、科学的に明らかになっていることは極めて少なく、将来の課題ではありますが、患者さんにはその点を正確な情報としてご理解いただき、単に栄養の摂取というだけでなく、日々の食卓に「彩り」を添え、食事の機会が楽しく豊かなものとなるようお手伝いができたらと考えております。具体的な活動についても、ご意見やご提案をいただけたらと考えておりますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
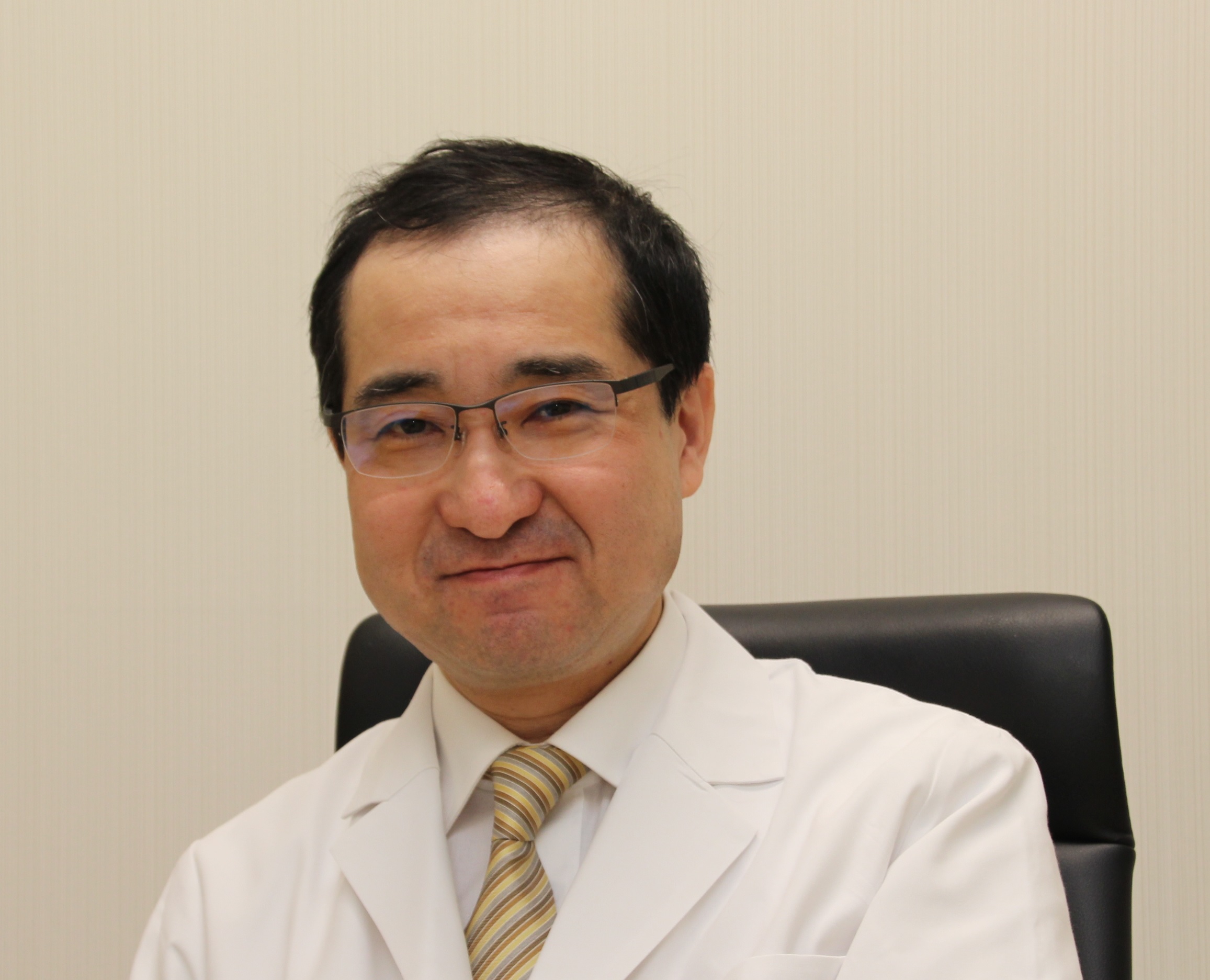
横山 正
よこやまIBDクリニック院長
横山 正からのメッセージ
皆さん、こんにちは。私は、名古屋で炎症性腸疾患(IBD)を中心に診療するクリニックの院長をしております。今回、「IBD患者さんの日常生活を彩る会」に理事として参画することとなりました。自己紹介を兼ねてこれまでの振り返りと今後について述べてみます。 私は平成元年に東京大学医学部を卒業し、国立がんセンターのレジデントなどを経て東京大学の第一外科教室(現 腫瘍外科)に入局しました。当時の教授は故 武藤徹一郎先生でIBDの外科治療のみならず内科的治療も行っており難病研究班の班長もつとめられました。その頃はサラゾスルファピリジンとステロイドが主な内科的治療法であり、IBD診療において外科の役割は現在よりも大きかったと思います。 東京大学でのIBDの勉強・修練ののち、名古屋の実家の胃腸科病院に帰りました。50歳になるまでは小さな胃腸科病院で潰瘍性大腸炎の大腸全摘術やクローン病の手術を多く行ってきました。一方で開業医となってからもIBDの内科的治療を勉強しながら行ってきましたが、とりわけ多くの治験に参加してきました。現在までにIBD領域の治験は37件行いましたが、サラゾスルファピリジンと通常のステロイドしかなかった出発点から現在皆さんの基本的治療となっているメサラジン製剤、新しいステロイドであるブデソニド製剤、そして生物学的製剤の開発へと治験を遂行してきました。これら薬剤が国内で保険認可されるには、当時は国内単独治験で多くの患者さんに参加していただく必要があり、患者さんと一緒に開発を進めてきたという思いです。そしてこれらの治験の多くは「彩る会」の日比理事長が統括して我々を先導していただきました。日比理事長からは常に「オールジャパン」でIBD患者さんのために仕事をしていくと訓示をいただき、開業医となった我々もオールジャパンの末席に参加させていただいて今日に至っています。平成27年に難病法が制定され、その中では「診断後はより身近な医療機関で適切な医療を受けることができる体制を目指す」とされていますが、IBDの専門医の間では病診連携が比較的円滑に行えているのはこのような土台があってのことと考えております。 今回、日比理事長から「彩る会」理事のお声がけをいただきました。IBDの研究がすすみ、使える薬も欧米に遅れることなく揃ってきましたが、同時に解決すべき社会的課題がまだまだ残っています。昨年まで私は愛知県医師会理事をしており、県から委託され県医師会に設置されている難病相談支援センターを担当しておりました。他の難病の勉強もさせていただく機会をえましたが、比較的身体的障害の少ないIBDの患者さんでも療養・就労両立支援や、進学就職支援などがまだまだ必要であると感じました。例えば、4月から就職が決まったが、就職後6か月間は有給休暇をもらえないので、月から金は休めず土曜日に診療を受けられないかという患者さんが多く私のところにいらっしゃいます。会社によっては雇用6か月以内でも有給休暇の取得は可能なので、個々の職場の事情は理解しますが、できるだけ優しい社会が実現してほしいと願っています。ある調査ではIBDの患者さんが仕事を休む最多の理由が定期的病院受診であって病状の悪化ではありませんでした。療養・就労両立支援用の意見書があることは医師の間でもまだ認知度が足りません。私たちは患者さんから社会的課題に対する声をいただき、専門家の集団としてこの解決を支援する必要があると考えます。私自身は開業医(実地医家)との連携や外科的視点からの活動を行ってまいります。 皆さんとともに優しい社会の実現に向けて活動していきましょう。
事業
- 国民に対する炎症性腸疾患に関する情報の提供及び啓発
- 炎症性腸疾患患者及びその家族の課題解決のための公共機関等に対する提言及び陳情
- 炎症性腸疾患患者の社会生活を支援するための相談及び指導
- 炎症性腸疾患患者とその家族・関係者の交流推進
- 国内外の関連医療施設ならびに学術団体との連絡及び協力
- 炎症性腸疾患に関するCSR活動に対する指導・助言・普及
- その他当法人の目的を達成するために必要な事業
アクセス・お問い合わせ先
- 一般社団法人 IBD患者さんの日常生活を彩る会
- 〒162-0834 東京都新宿区北町9-1 102 北町事務所
電話:03-6780-8394
E-mail:info@ibd-irodoru.com
久松 理一からのメッセージ
1991年卒で医師になって34年間のうちほぼ30年間IBDと関わってきたことになる。私が消化器内科医になった頃はIBDの治療薬はステロイド、サラゾスルファピリジン、経腸栄養療法しかなかった。IBD患者の入院期間は長く、いかに外来に戻すかが大きな目標であり、とても社会復帰や結婚・出産といったところまでケアはいき届いていなかったと思う(議論すらなかったかもしれない)。その後、分子標的治療薬の開発が進み、明らかに予後が改善したことで医学的な疾患活動性コントロールだけでなく、患者さんの生活の質の改善が求められるようになった。IBDの特徴は比較的若い患者さんが多く、そして慢性疾患であるということである。この2つを満たすのは消化器疾患の中でもIBDぐらいであり、非常に特殊である。医師になりたての頃に受け持った若年の患者さんが、現在の自分の外来にお子さん連れで通院していたりする経験はおそらく一般の消化器内科医で経験することはない。言い換えればIBD診療の成否は単に内科治療が奏功したか、外科手術を回避できたか、では決まらず、10年、20年経って判明するものだと思う。そうすると自分一人で全ての患者を一生にわたって診療することは不可能であり、そこには医療の均てん化、多職種連携、地域医療連携、社会支援体制などさまざまな要素が絡んでくる。現在、厚労省難病班(難治性炎症性腸管障害に対する調査研究班、通称IBD班)の研究代表者を務めているが、研究班の大きな役割はまさに医療の均てん化、社会支援体制の充実にあり、オールJAPAN体制で多くの成果をあげている。一方で研究班の弱点の1つに患者さんやその家族との直接の関わりが希薄であることが挙げられる。班のホームページには患者さんや家族に向けた資料も豊富にあるが、そこへの患者さんからのアクセスはまだ限られている。製薬企業も製品に直接関係のない患者支援やIBD啓発活動に力を入れるようになってきているが、同様に患者さんからのアクセスは限定的なようである。自分は彩る会の役割は日本のIBD社会支援体制のハブになることではないかと考えている。研究班、企業、学会、一般医療従事者、そして患者さんをうまく結びつける潤滑油のような役割が果たすことができればこの会の存在価値は大きなものになると思う。事実、日本の難病制度において、このような役割を担っている団体はほとんどない。彩る会の成功は多くの疾患においてモデルケースになりうると信じている。